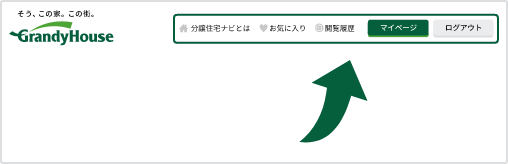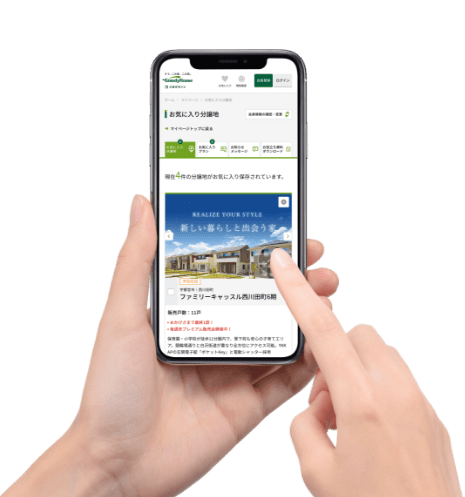住宅購入をお考えの方や、最近の地震のニュースを見て自宅の安全性が気になっている方も多いのではないでしょうか。特に木造住宅にお住まいの方は、地震に対する不安を抱えていることも少なくありません。
「木造住宅は地震に弱いと聞くけれど、本当のところどうなのかしら」「地震が起きても家族の安全を守れる住宅を選びたい」といった声をよく耳にします。
この記事では、木造住宅の耐震性の特徴や、地震に対する備えについて詳しく解説していきます。
目次
木造住宅の耐震性はどれくらい?

木造住宅の耐震性は、建築時期によって大きく異なっていることをご存知でしょうか。
1981年に建築基準法が改正され、新耐震基準が設けられたことで、それ以降に建てられた木造住宅は高い耐震性能を備えています。
さらに2000年には木造住宅の耐震基準が更に改正され、壁の配置バランスや接合部の規定が強化されました。
地震に対する木造住宅の特徴として、建物自体が柔軟に揺れを吸収できる構造になっているため、適切な耐震設計がなされていれば倒壊するリスクは低くなります。
新耐震基準後の木造住宅の耐震性
新耐震基準後の木造住宅の多くは、地震に対して十分な強度を持っています。2000年以降に建てられた住宅では、震度6強から7程度の大地震でも倒壊しにくい構造となっているため、安心して暮らすことができます。
その理由は、新耐震基準では建物に必要な耐震性能が明確に定められているからです。具体的には、中規模の地震(震度5程度)では建物が損傷せず、大地震(震度6以上)でも人命に危害が及ばない程度の強度を確保することが義務付けられています。
旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震性
旧耐震基準で建てられた木造住宅は、地震に対する安全性が十分とはいえない状況にあります。1981年以前に建てられた木造住宅は、現代の耐震基準を満たしていないため、大地震の際に倒壊するリスクが高くなっています。
その理由として、旧耐震基準時代は現在ほど地震に対する研究が進んでいなかったことが挙げられます。当時の木造住宅では、壁の配置や接合部の補強が十分ではなく、また基礎の強度も現代の基準と比べて不十分でした。
ただし、旧耐震基準の木造住宅であっても、耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強工事を実施することで、新耐震基準と同等の安全性を確保することができます。
耐震補強工事では、壁の増設や基礎の補強、金物による接合部の補強などを行い、建物全体の耐震性能を向上させます。
木造住宅のメリット

木造住宅には、建築コストを抑えられることや住み心地の良さなど、さまざまな魅力があります。
建築費用を抑えられる
木造住宅の最大のメリットの1つが、建築費用を抑えられる点です。鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造と比較すると、建築コストを抑えることが可能となっています。
この費用面でのメリットが生まれる理由は、主に材料調達と施工の両面にあります。木材は比較的入手が容易で、日本国内での流通量も豊富です。
また、木造住宅の建築技術は日本の大工の伝統的な技術として確立されているため、施工にかかる人件費も他の工法に比べて抑えられます。
建築費用を抑えられるとはいえ、耐震性や耐久性を犠牲にするべきではありません。適切な耐震設計と施工、そして定期的なメンテナンスを行うことで、安全で快適な木造住宅を実現することができます。
断熱性が高く快適に暮らせる
木造住宅の大きな特徴として、優れた断熱性能が挙げられます。木材は空気を多く含む構造のため、熱を伝えにくい性質を持っており、室内を快適な温度に保ちやすい特徴があります。
これは、木材の細胞構造に無数の小さな空気層が存在するためです。この自然の断熱材としての特性により、夏は涼しく冬は暖かい室内環境を実現できます。
デザインの自由度が高い
木造住宅の魅力的なポイントの1つが、自由度の高いデザイン性です。木材は加工がしやすく、さまざまな表現が可能なため、住む人の好みやライフスタイルに合わせた理想の住まいを実現できます。
その理由として、木材は切断や接合が比較的容易で、曲線的なデザインや複雑な形状にも対応できる特性を持っています。また、木の種類も豊富で、それぞれの木材が持つ独特の色合いや木目を活かした意匠的な演出が可能です。
設計段階で建築家や工務店としっかり打ち合わせを重ねることで、理想の住まいを具現化することができます。
木造住宅のデメリット
木造住宅には他の工法と比べて気になる弱点がいくつかあります。特に防音性の低さは、住む場所や家族構成によっては大きな課題となってくるでしょう。
防音性が低い
木造住宅は、RC造やS造の建物と比べて防音性が劣る傾向にあることが大きな特徴です。特に上下階や隣室からの生活音が伝わりやすいという性質があります。
これは軽量な構造であるために振動が伝わりやすいことが主な要因となっています。具体的には、以下のような音が気になりやすい傾向にあります。
階段や2階の足音
テレビやオーディオの音
子どもの飛び跳ねる音
洗濯機やエアコンの振動音
ただし、最近の木造住宅では防音対策技術が進歩しており、適切な施工方法を選べば音の問題は大幅に改善できます。
例えば、防音材を床や壁に入れたり、二重床や二重天井を採用したりすることで、かなりの遮音効果が期待できるでしょう。
シロアリの被害に遭う可能性がある
木造住宅では、シロアリによる被害が発生するリスクがあり、適切な予防と対策が重要になってきます。特に日本の高温多湿な気候は、地域によってはシロアリの活動を活発にする環境となっています。
シロアリは木材を食害することで家屋に重大な損傷を与え、最悪の場合は建物の構造的な強度を低下させる可能性があります。これは地震に対する耐震性能にも影響を及ぼす要因となるため、早期発見と予防が欠かせません。
シロアリ被害を防ぐためには、以下のような予防対策と定期的な点検が効果的です。
床下や壁の定期的な点検
床下換気の確保と湿気対策
防蟻処理剤の定期的な散布や設置
木造住宅で暮らす上での注意点

木造住宅で快適に暮らすためには、いくつかの重要なポイントに気を配る必要があります。耐震性や遮音性といった住宅の基本性能は、日々の暮らしの安全性や快適性に大きく影響を与えるでしょう。
耐震性に気をつける
木造住宅に暮らす上で、耐震性への配慮は最も重要な要素の1つです。特に地震大国である日本では、定期的な点検と適切な対策が欠かせません。
まず、お住まいの木造住宅の耐震診断を実施することをおすすめします。専門家による診断で建物の状態を正確に把握することで、必要な対策を明確にできます。特に1981年以前に建てられた築年数が古い住宅では、耐震補強工事の必要性を見極めることが重要になってきます。
また、家具の転倒防止も重要な対策の1つです。地震の際に家具が倒れてくることで、けがをしたり避難経路が塞がれたりする危険性があります。
L字金具やつっぱり棒を使用して家具を固定し、安全な室内環境を整えていきましょう。
遮音性について対策する
木造住宅の防音性を高めるためには、適切な対策が重要です。特に生活音が気になる場合は、いくつかの効果的な方法を組み合わせることで、快適な住環境を実現できます。
防音対策の基本となるのが、床や壁、天井への防音材の施工です。防音材には吸音材や遮音材、制振材など様々な種類があり、それぞれの特性を活かした使い方が可能です。
特に床の防音対策は重要で、二重床構造の採用や防音マットの設置が効果的な方法となります。
まとめ
近年に建築された木造住宅は、地震に対する安全性が大きく向上しています。ただし、1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅については、耐震診断や必要に応じた補強工事の検討が望ましいでしょう。
木造住宅には、コストを抑えられることや断熱性の高さ、デザインの自由度が高いといったメリットがあります。一方で防音性の低さやシロアリ被害のリスクといったデメリットもあることを理解しておく必要があります。
地震に備えた暮らしのためには、まず自宅の耐震性を把握することから始めてみましょう。建築年や構造について確認し、不安がある場合はグランディハウスへぜひご相談ください。
関連記事はこちら

2022.12.09
木造住宅とは?構造の特徴やメリット・デメリットを解説!

2025.01.24
住宅ローン返済中に地震に被災したらどうなる?支援制度について解説

2024.12.24
新築物件に地震保険は必要?相場やメリットについてご紹介します