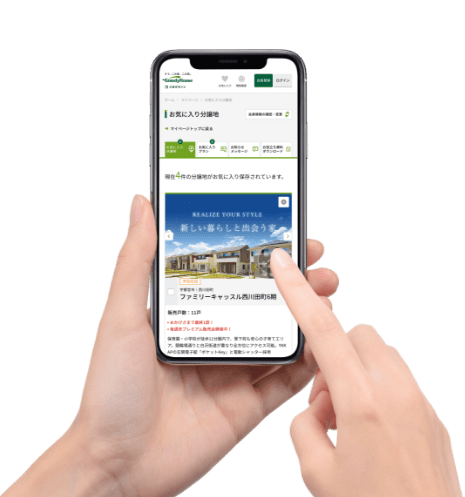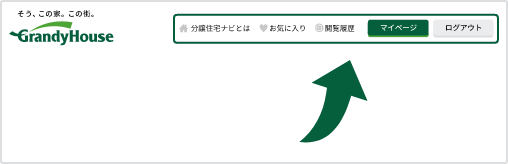2024年は能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報など、災害が印象的だった1年でした。
災害が多い日本において、「自宅を可能な限り安全な環境にしたい」「耐震性能の高い家で安心して暮らしたい」と考える方も多いのではないでしょうか。
地震大国である日本においては『100年や50年に一度くる』大地震への備えも必要です。
一昔前までは大地震の際、建物にどのように影響するかは一般消費者にわかりにくかった状況が長く続きました。
1995年の阪神淡路大震災の経験を切っ掛けに新たな法律も2000年から施行され、良質な住宅を安心して取得し居住できるよう、一目でわかる住宅性能の表示基準として示されたのが「耐震等級(倒壊等防止、損傷防止)」でした。
本記事では、耐震等級とはどのような指標なのか、そのメリットやデメリットについて解説します。耐震等級の高い家を選ぶ(建てる)ことで、地震に強く安心できる住まいを手に入れることができるでしょう。
目次
耐震等級とは

耐震等級は、2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」内で定義づけられている住宅性能表示に基づく指標です。
この等級は、建物が地震に対してどれだけ強いかを示すもので、数字が大きいほど耐震性能が高くなります。
参考:住宅の品質確保の促進等に関する法律|e-Gov法令検索
耐震等級は1から3まであり、建物の構造や建物の重さ、耐力壁の量、床の耐力によって決定されます。耐震等級の高い家を選ぶ(建てる)ことで、地震に対する備えを強化できます。
建築基準法の耐震基準と耐震等級との違い
建築基準法での『耐震基準』は、建物の構造や重さ、耐力壁の量とバランスを定めており、また品確法での『耐震等級』では建築基準法(耐震基準)の定めはもちろんの事、床の耐力(水平耐力)も求められています。
【耐震基準】
1981年(昭和56年)及び2000年(平成12年)の改正建築基準法で新たに定められた、最低限の安全性を確保するための基準です。
【耐震等級】
2000年(平成12年)、新たに施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、耐震基準を上回る耐震性能を評価するための指標となっています。
耐震等級1・2・3について
耐震等級は建物の耐震性能を示す指標で、1から3までの3段階に分かれていて数字が大きくなるほど耐震性能が高く、地震に対する安全性が向上します。
それぞれの等級について詳しく解説します。
耐震等級1
【耐震等級1】(建築基準法で定められている最低限の耐震性能を満たす水準)
・倒壊等防止
数百年に一度発生する地震力に対し、建物が倒壊や崩壊しない程度(震度6強から7程度=阪神・淡路大震災や熊本地震クラスの揺れを想定)
・損傷防止
数十年に一度発生する地震力に対し、建物が、損傷しない程度(震度5強程度=東京都で発生した震度を想定)
耐震等級1は、建築基準法での耐震基準と同等の性能を指標します。つまり、最低限の安全性を確保している建物です。
『例えば・・・』
建物が、震度6強から7程度の地震は倒壊や崩壊はしない程度であるが、震度6弱以上では一定程度建物に損傷が起きる可能性があるという事になります。
耐震等級2
【耐震等級2】
・倒壊等防止
数百年に一度発生する地震力の1.25倍に対し、建物が倒壊や崩壊しない程度
・損傷防止
数十年に一度発生する地震力の1.25倍に対し、建物が、損傷しない程度
耐震等級2と同等の性能を有している建物では、一般的に災害時の避難所として指定されることが多い学校や、病院などの建物に採用されており、また長期優良住宅認定基準での必須項目にもなっています。
耐震等級3
【耐震等級3】
・倒壊等防止
数百年に一度発生する地震力の1.50倍に対し、建物が倒壊や崩壊しない程度
・損傷防止
数十年に一度発生する地震力の1.50倍に対し、建物が、損傷しない程度
耐震等級3と同等の性能を有している建物では、一般的に災害時の救護活動・災害復興の拠点となる消防署・警察署などの建物に多く採用されています。
また、震度7の揺れが立て続けに2回起こった熊本地震では耐震基準での建物で1度目は耐えたが2度目の地震で倒壊・崩壊した住宅もあった中、耐震等級3の住宅は2度の震度7に耐えていたことが、専門家の調査によって明らかになっています。
耐震等級3を実現するメリット

耐震等級3を実現することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
2つのメリットについて解説します。
安全性が高い
耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられるだけの性能・耐震強度水準です。
住宅性能表示制度で定められた耐震性の中でも最も高いレベルであり、一度大きな地震を受けてもダメージが少ないため、余震後も住み続けられる実績(2016年熊本地震より)から、耐震性の高い建物の中では一番安全と言われてます。
また木造建築物において、一般的に耐震等級の高い建物では以下の点での特徴が見受けられます。
壁を強化:筋交いを多く入れる、構造用合板や耐力面材を使用する
床と屋根を強化:床に構造用合板を張る。軽い屋根材を使い、揺れにくくする
柱と梁の接合部を強化:接合金物を取り付ける
基礎を強化:ベタ基礎で、コンクリートを厚くする
梁の強化:集成材など強度の高い材を使う
参考:「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント
地震保険料が割引になる
耐震等級3を取得することで、地震保険料が50%割引になります。
割引率は耐震等級によって以下のように変動します。
耐震等級 |
割引率 |
3 |
50% |
2 |
30% |
1 |
10% |
割引を受けるためには住宅性能評価書や、耐震性能評価書などが必要になります。
地震保険料の割引については、各損害保険会社にご確認ください。
耐震等級を高める場合のデメリット
耐震等級を高めることは住宅の安全性を向上させる上で重要ですが、いくつかの注意点があります。
2つの注意点について解説します。
間取りや構造が制限を受ける
耐震等級3を実現するには、建物の構造や間取りに一定の制限が加わることを理解する必要があります。これは、高い耐震性能を確保するために避けられない面があるためです。
具体的には、以下のような制限が生じる可能性があります。
壁量の増加:耐震性能を高めるため、壁の量を増やす必要があります。これにより、開口部(窓やドア)の配置や大きさに制限が出る場合があります。
間取りの制約:耐力壁の配置の関係で、極端に壁の少ない間取りは難しい場合があります。
吹き抜けの制約:大空間や、極端に大きな吹き抜けがある間取り
デザイナーによる住宅:耐力壁のバランスが悪い、極端な間取りや外観デザイン
例えば、構造上の制約から開口部の大きいワイドなリビングが難しいケースが考えられます。
しかし、こうした制限があるからこそ、耐震等級3の建物は高い安全性を実現できるのです。間取りや構造の制限以上に安全面においてメリットが大きいため、新築物件を選ぶ際は耐震等級3を満たす建物をおすすめします。
建設費用が高くなる
耐震等級3を実現するには、追加の構造補強や部材、建材の使用が必要となるため、建設費用が高くなる傾向にあります。
耐震等級3の建設費用が高くなる主な理由は以下の通りです。
壁量計算や設計にかかる費用の増加
耐震性能の高い建材や部材の使用
基礎や壁の補強に伴う材料費と工事費の上昇
より厳密な施工管理による人件費の増加
ただし、この追加コストは長期的な視点で見れば、投資として捉えることができます。耐震等級3の住宅は地震に対する安全性が高く、将来的な修繕費用の削減や資産価値の維持にもつながる可能性があります。
まとめ
耐震等級について、その基準やメリット・デメリットについて解説しました。
安全性の向上や地震保険料の割引など、そのメリットは大きいと言え、大震災がいつ発生してもおかしくない昨今において、地震大国の日本で安心して暮らすためには、耐震等級3の建物を選ぶ(建てる)ことが望ましいでしょう。
会員だけの便利な機能を使って
サクサク住まいを探そう!
- 非公開物件が閲覧できる
- お気に入り保存・比較できる
- 検索条件が保存できる
- お役立ち資料をダウンロード
- 気になる物件のおトクな情報をメールでお知らせ