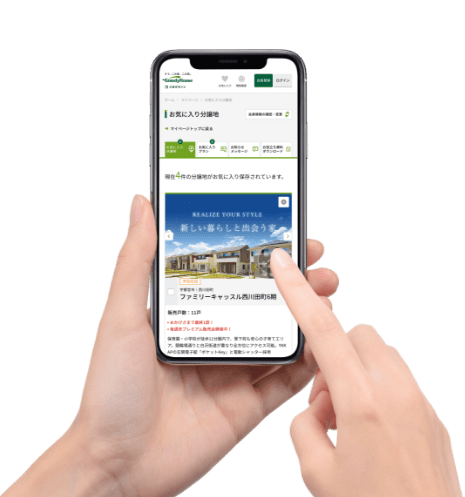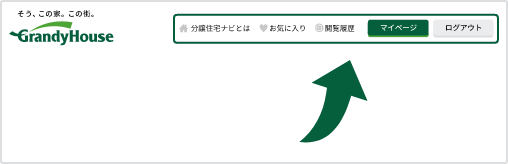二世帯住宅を建てようと思っている方の中には、どのくらいの費用がかかるのか気になっている方もいるでしょう。二世帯住宅は、建てる間取りや共有する部屋の数によって費用が異なるため、予算を考える際は合わせて間取りも検討する必要があります。
当記事では、二世帯住宅にかかる費用を住宅のタイプに分けて紹介した上で、実際に予算を考える際のポイントについて解説します。理想の二世帯住宅を建てるためにぜひお役立てください。
1.【タイプ別】二世帯住宅にかかる費用は?
二世帯住宅は居住する世帯が多く必要な面積や住宅設備も増えるため、一般的な住宅よりも費用が高くなる傾向がありますが、住宅のタイプによって必要な費用は異なります。世帯間の共有部分を増やすほど費用が安くなる傾向があるため、それぞれの世帯のライフスタイルを考慮した上で、住宅のタイプや間取りを検討しましょう。
ここでは、二世帯住宅の費用相場を3つの住宅タイプ別に紹介します。それぞれの住宅タイプの特徴も併せて確認した上で、二世帯住宅の購入検討を進めましょう。
1-1.完全同居型
完全同居型の二世帯住宅とは、単世帯用住宅のような1つの住宅の中で、親世帯と子世帯が同居するタイプのことです。子世帯にミニキッチンやサブリビングを設ける場合もありますが、基本的にはキッチンやリビング、お風呂(浴室)、トイレなどの住宅設備を2つの世帯で共有します。
完全同居型は共有部分が多く、お互いのプライバシーを確保することが難しいというデメリットがあります。生活リズムが異なる場合には、足音や生活音などの配慮が必要となる点にも注意しましょう。
一方で、世帯間の関係が良好な場合は、「お互いに協力し合う生活」を選択できるメリットがあります。住宅設備が少ないため光熱費を抑えやすく、将来一世帯での生活となった場合にもデッドスペースが生まれにくい点もポイントです。
完全同居型は2つの世帯で共有する部分が多く、3つの二世帯住宅タイプの中で最も建築費用を抑えやすい傾向があります。立地や建物の面積などの条件にもよりますが、坪単価は65万~100万円ほど、建物の費用は2,000万~3,500万円ほどを目安として家づくりを考えるとよいでしょう。
1-2.部分共有型
部分共有型の二世帯住宅とは、同じ建物の中で一部の設備・空間を共有しながら、主な居住空間は各世帯で確保するタイプを指します。玄関やお風呂、洗面所などを共有するケースが多いと言われていますが、共有する部分・空間は家族のライフスタイルや価値観によってカスタマイズすることが可能です。
部分共有型の場合、世帯間でのトラブルを防ぐためにも、共有部分の使い方に関する取り決めをしておくことが非常に重要となります。共有部分を使用する時間・タイミングが重ならないようにしたり、掃除や光熱費負担の割り当てを決めたりするなど、双方が不満を抱えないよう予防策を講じておきましょう。
共有部分に関する相談や配慮が必要となる一方で、完全同居型と比べてプライバシーを確保しやすい点は部分共有型のメリットと言えます。共有部分があるため、暮らしの中で世帯間のコミュニケーションがとりやすいのも魅力的なポイントです。
部分共有型は完全同居型よりも共有部分が少ないものの、一部の設備・空間は共有するため、2つの世帯が完全に分離するタイプよりも建築コストを抑えられます。建築費用は単世帯用の住宅よりも2~3割ほど高く、坪単価は80万~130万円程度、建物の費用は2,500万~4,500万円程度を想定しておくとよいでしょう。
部分共有型の二世帯住宅の場合、住宅の立地や面積だけでなく、共用する設備や空間の種類・内容によっても建築費用が大きく異なります。理想とするライフスタイルと予算とのバランスをよく考えた上で、共有部分の計画を立てましょう。
1-3.完全分離型
完全分離型の二世帯住宅とは、1つの建物の中で親世帯と子世帯の居住空間が完全に分かれているタイプのことです。完全分離型には「1階に親世帯・2階に子世帯」の「横割りタイプ」と「住宅の中央付近に壁をつくり居住空間を分ける」といった「縦割りタイプ」の2種類があります。
完全分離型は居住空間が各世帯で完全に分かれているため、もう一方の世帯の様子に目が届きにくいというデメリットがある点に注意しましょう。一方で、プライバシーを十分に確保しながらも、必要なときにはもう一方の世帯にすぐ駆け付けられる点は大きなメリットと言えます。間取りの自由度が高いことも完全分離型の魅力です。
完全分離型の場合はキッチンやお風呂、洗面所などの住宅設備が各世帯に必要となるため、その分必要な面積や設備が増え、建築コストも高くなります。二世帯住宅の3つのタイプの中では最もコストがかかりやすく、坪単価は85万~150万円ほど、建物は3,000万~5,000万円ほどが費用相場となります。
2.二世帯住宅の費用を考える際のポイント3つ
二世帯住宅は単世帯用の住宅よりも建築費用が高くなる傾向があるため、以下のポイントを押さえた上で予算を考えることが大切です。
◆二世帯住宅の費用を考える際に押さえたい3つのポイント
- 費用負担は話し合って決める
- 税金の軽減措置や優遇制度を知っておく
- 費用を抑える工夫をする
ここでは上記の3つのポイントについて詳しく解説します。
2-1.費用負担は話し合って決める
二世帯住宅を建てる上で、親世帯と子世帯の費用分担を事前に話し合っておくことは非常に重要なポイントです。「登記」と「相続」の両方を意識した上で、それぞれの費用負担を具体的に決めるようにしましょう。
土地や住宅の登記は、基本的には費用を出した割合で決まります。たとえば、建築費用の3割を親世帯・7割を子世帯が負担した場合、建物の所有権の持ち分は親世帯が3割分・子世帯が7割分となります。このケースで建物の所有権をどちらか一方の名義にしてしまうと、贈与税がかかる場合があるため注意が必要です。
また、二世帯住宅に住んでいない兄弟姉妹がおり、親世帯が所有権の一部またはすべてを持っている場合、将来相続トラブルが起こる可能性があります。親世帯も費用を負担する場合には、将来の相続を見越して兄弟姉妹との話し合いを済ませておくことも重要です。
2-2.税金の軽減措置や優遇制度を知っておく
住宅を新築する際には、単世帯用か二世帯用かを問わず、条件を満たせば不動産取得税や固定資産税の軽減措置を受けられます。二世帯住宅の場合、決められた要件を満たして「二戸分の住宅である」と認定されれば、二戸分の軽減措置を受けられることを押さえておきましょう。
二世帯住宅が二戸分と認定される要件は自治体によって異なりますが、多くの場合は登記の内容によらず「構造上・利用上の独立性が確保されていること」がポイントです。居住スペースが完全に分かれているタイプや、部分共有型で共有スペースを鍵付きの扉で仕切るタイプの住宅は該当する可能性が高いでしょう。
また、相続時には自宅の土地の評価額が80%減額される特例があります。二世帯住宅に住む親世帯・子世帯が同一の世帯として登記されており、子世帯が土地を相続して居住・保有し続ける場合に相続税の優遇措置を受けられます。親世帯と子世帯が別の世帯として登記(区分登記)されている場合は、相続税の優遇措置を受けられないことに留意してください。
2-3.費用を抑える工夫をする
二世帯住宅の建築費用を抑えるには、下記のようなコスト削減のための工夫をすることも重要です。理想のライフスタイルと予算のバランスを考えながら、実施可能なコスト削減策に取り組みましょう。
◆二世帯住宅の費用を抑える工夫(例)
- 凹凸のある構造・間取りを避け、正方形などシンプルな形状の建物にする
- なるべくシンプルな形状の屋根を選ぶ
- 水回りの部屋を減らしたり間取り設計をシンプルにしたりして、配管設備をまとめる
- 廊下を減らす
- 階段を共用にする
- 設備や資材のグレードを検討する
まとめ
二世帯住宅には大きく分けて完全同居型・部分共有型・完全分離型の3種類があり、それぞれ間取りや費用が異なります。一般的に共有部が多くなるほど価格は安く抑えられるため、予算や生活スタイルを考慮しながら親世代子世代の両方が笑顔で暮らせる二世帯住宅を建てましょう。
グランディハウスでは、住みやすい理想の家づくりを応援しています。一戸建ての購入を検討される際は、注文住宅をご検討中の方もぜひ一度グランディハウスにご相談ください。
会員だけの便利な機能を使って
サクサク住まいを探そう!
- 非公開物件が閲覧できる
- お気に入り保存・比較できる
- 検索条件が保存できる
- お役立ち資料をダウンロード
- 気になる物件のおトクな情報をメールでお知らせ