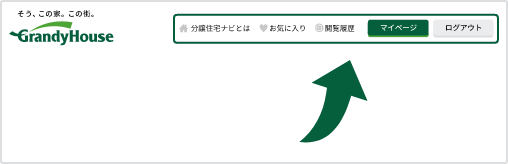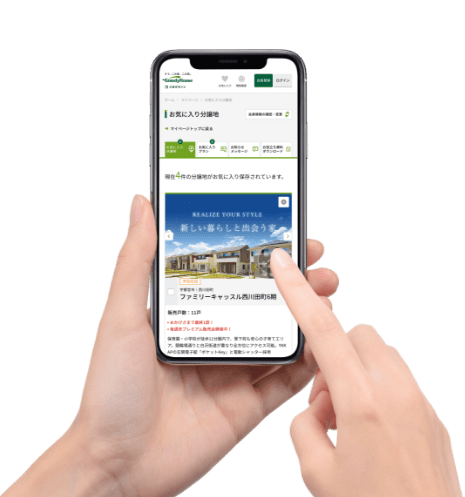家を建てるとき、無駄のない土地利用で広い家を建てたいと考える方は多いでしょう。しかし、家を建てる上では「建蔽率」を守る必要があり、自由な広さで家を建てられるわけではありません。家の立体的な大きさについても「容積率」による建築制限があります。
当記事では、建蔽率・容積率の基礎知識や調べ方、オーバーした場合の問題点などを解説します。家を建てるときに失敗したくない方は、建蔽率・容積率に代表される建築基準に注意して建物の面積を決めましょう。
1.建蔽率・容積率とは?

建蔽率(建ぺい率)とは、敷地面積に対して建築面積が占める割合のことです。建蔽率は下記の計算式で求めます。
・建蔽率の計算式
建蔽率(%)=建築面積÷敷地面積×100
一方の容積率とは、敷地面積に対して延床面積が占める割合のことです。容積率は下記の計算式で求めます。
・容積率の計算式
容積率(%)=延床面積÷敷地面積×100
建物の建蔽率・容積率は、建築基準法や都市計画法によって上限が定められており、上限値は用途地域ごとに異なります。家を建てるときは建蔽率・容積率が規定の割合以下になるよう設計しましょう。
出典:e-GOV 法令検索「建築基準法」
建ぺい率とは?計算方法・容積率との関係から緩和措置・注意点まで
1-1.建蔽率と容積率が定められている理由は?
建築基準法で建蔽率と容積率が定められている理由は、下記の3点が挙げられます。
・火災のとき延焼を防ぐため
建物が密集している状態では、火災のときに火が建物を伝って一帯に燃え広がりやすくなります。建蔽率が制限されていると敷地内に適度な空地を確保できるため、火災が起きても延焼を防ぐことが可能です。なお、防火地域内で耐火性に優れた建物を建てる際は、建蔽率が緩和されるケースもあります。
・風通しや日当たりを確保するため
建蔽率は、快適な住環境を作る上でも重要です。建蔽率の制限によって建物同士の距離を広く取ることで、住居の風通しや日当たりを確保できます。
・人口をコントロールするため
容積率を制限することで、建物一棟あたりの収容人口をコントロールできます。建物の収容人口は地域人口と密接なつながりがあり、道路・公園・上下水道などの市街地整備を計画的に行う上で重要なポイントです。
1-2.建蔽率・容積率の調べ方
家を建てる地域の建蔽率・容積率が分からないときは、不動産会社に確認しましょう。不動産会社が販売する土地であれば、物件情報の中に建蔽率・容積率の上限が明記されているケースもあります。
建蔽率・容積率は市区町村に問い合わせをして調べることも可能です。土地の住所を控えておき、都市計画部・都市計画課などの街づくりを担う部署に問い合わせると、土地の建蔽率・容積率を教えてもらえます。
2.建蔽率・容積率をオーバーしてしまったらどうなる?
建蔽率・容積率をオーバーした建物は「違反建築物(違法建築物)」として扱われます。
違反建築物とは、建築基準法や都市計画法などの法律に違反した建築物のことです。行政の完了検査後に改めて建築確認申請をせずに増築したり、リフォームで増築したりすることで、違反建築物に該当する可能性があります。
また、過去の建築基準法などには適合していたものの、現行法と照らし合わせると建蔽率・容積率をオーバーしている建物は「既存不適合建築物」として扱われます。既存不適合建築物は違反建築物ではないものの、規模の大きい増改築をする場合は現行法に適合するように建て替えることが必要です。
以下では、家の建蔽率・容積率がオーバーした場合の問題点を3つ紹介します。
2-1.罰則が与えられる
建蔽率・容積率のオーバーは建築基準法に違反しているため、罰則が与えられる恐れがあります。
罰則の対象者は、主に建築を請け負った建築業者や建築士です。違反建築物が発覚した場合は基本的に、建築士免許の取り消しや業務停止などの行政処分が行われます。悪質な違反建築が行われていると見なされた場合は、罰金・懲役などの刑事罰が科せられるケースもあるでしょう。
建築業者・建築士が罰則を受けることは、建築を依頼した施主とも無関係ではありません。罰則を受けた建築業者は工事を進められず、家の建築工事が中断してしまいます。
2-2.ローンが下りなくなる

金融機関が提供する住宅ローンは、建築対象の物件を担保としたときの評価によって融資額を決定します。建蔽率・容積率をオーバーした家は担保価値が低くなり、ローンが下りなくなる点に注意してください。
金融機関が物件を担保とする理由は、万が一ローンの返済が滞ったときに抵当権を実行して物件を競売にかけ、残債分を取り戻すためです。
しかし、建蔽率・容積率をオーバーした違反建築物や既存不適合建築物では競売にかけても値段が付きにくい傾向があります。当該建築物の担保価値が低いと金融機関が判断すれば、ローン申請は却下されるでしょう。
2-3.
建蔽率・容積率をオーバーした建物は売却しにくくなる点にも注意してください。
違反建築物に該当する建物には、所有者に違反部分を是正する義務があります。たとえ違反建築物を売却しても是正義務自体は消滅せず、新しい所有者に移ります。
また、違反建築物はローンが下りないため、物件の購入方法は現金一括のみとなるでしょう。是正義務が発生する上に、購入方法が現金一括のみでは購入希望者が現れにくいため、建蔽率・容積率をオーバーした建物は売却しにくいと言えます。
3.【建蔽率・容積率以外にも!】気を付けるべき建築基準

家を建てるときは建蔽率・容積率さえクリアしていればよいわけではありません。建物の広さにかかわる建蔽率と、立体的な大きさにかかわる容積率の他に、高さにかかわる建築基準も押さえることが重要です。
最後に、建蔽率・容積率と並んで気を付けるべき「高さ制限」「斜線制限」について解説します。
3-1.高さ制限
高さ制限とは、敷地内に建てられる建物の高さを制限する建築基準です。
高さ制限は都市計画法や各自治体の条例によって定められており、具体的な高さの上限は用途地域や高度地区の地域区分により異なります。
一例として、第一種低層住居専用地域で定められている高さの上限は10mもしくは12mです。第一種低層住居専用地域は一戸建てや低層マンションを建てるための住居系地域であり、景観や住環境の保護を目的として高さ12m以上の建物は制限されています。
3-2.斜線制限
斜線制限とは、建物の各部分における高さを制限する建築基準です。斜線制限は高さ制限の1種であり、制限する内容の違いによって3つの斜線制限が存在します。
・隣地斜線規制
隣地斜線規制とは、隣地境界線の高さ20m部分から1:1.25の勾配を持つ斜線を引き、斜線から建物の高さがはみ出さないように規制する建築基準です。隣地の日照・採光・通風などを確保し、良好な住環境を保つことを目的としています。
なお、高さ制限で高さの上限が10mもしくは12mと制限されている地域では、高さ20m以上を規制する隣地斜線規制は適用されません。
・道路斜線制限
道路斜線制限とは、前面道路の反対側から1:1.25(用途地域や道路幅員によっては1.5)の勾配を持つ斜線を引き、建物の高さを斜線内に収めるよう制限する建築基準です。道路の日照・採光・通風などを確保することを目的としています。
建物の作る日影が道路に影響する20~50mの適用範囲(用途地域により異なる)では、建物の高さは道路斜線制限に適合させる必要があります。
・北側斜線制限
北側斜線制限は、敷地北側にある隣地境界線の高さ5mまたは10m部分から1:1.25の勾配を持つ斜線を引き、建物の高さを斜線内に収めるよう制限します。北側隣地に位置する家の日照権確保などを目的とした建築基準です。
出典:国土交通省「住宅団地の再生に関係する現行制度について」
建蔽率・容積率はもちろん、高さ制限や3つの斜線制限も守ることで、建築基準法などの法令に違反しない家を建てられます。
まとめ
建蔽率とは敷地面積に対する建築面積の割合であり、容積率とは敷地面積に対する延床面積の割合です。建蔽率は火災時の延焼防止や風通し・日当たりの確保、容積率は人口のコントロールを目的として、建築基準法で上限が定められています。
建蔽率・容積率が上限をオーバーすると違反建築物と見なされ、罰則が科されたりローンが下りなかったりするなどの問題が生じます。家を建てるときは建蔽率・容積率だけではなく、高さ制限・斜線制限にも注意しましょう。
グランディハウスでは施主様が安心して施工を任せられる家づくりを行っております。建築基準などを遵守した家づくりは、グランディハウスにご相談ください。